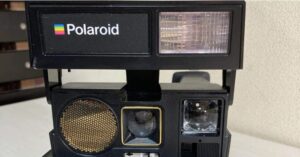AirPod Proが「簡易補聴器」に? 噂のヒアリング補助機能を徹底検証

近年、AppleのAirPods Proに搭載された「ヒアリング補助」機能が大きな話題を呼んでいます。これは、専用のアプリと連携し、AirPods Proを簡易的な補聴器のようにカスタマイズして使用できるという画期的な機能です。高価な専門機器に手が届きにくい層や、軽度な聴覚サポートを必要とする人々にとって、身近なワイヤレスイヤホンがこの役割を果たせるというのは、まさに朗報と言えるでしょう。
私もAirPods Proを所有しており、この補助機能の存在を知りつつも、その用途には使用していませんでした。しかし、その実力を確かめるべく、今回、実際にこの「聴力補助」機能を試してみました。(本記事はプロモーションを含みます)
ステップ1:Appleのヒアリングチェックを受ける
この機能を使用するための最初の手順は、自分の聴覚特性をAirPods Proに認識させることです。 まず、AirPods Proをケースから取り出し、耳に装着すると、iPhoneの「設定」メニューに「AirPods Pro」専用の設定項目が表示されます。その中にある「Appleのヒアリングチェックを受ける」というメニューをタップします
画面の指示に従うと、健康診断で行う聴覚測定を彷彿とさせるプロセスが始まります。様々な周波数の「ポーン」という試験音が片耳ずつ聞こえてきます。ユーザーは音が聞こえたら画面をタップするという作業を繰り返します。結構な数のテスト音に対して診断を受けると、最終的に聴覚能力の診断結果が表示されます。結果は「難聴の可能性はほとんどない」、「軽度難聴」、「中等度難聴」などの分類で示されます。
さらに、詳細なデータとして、何Hzの音がどの程度のデシベル(dB)で聞こえるのかという具体的なグラフも表示させることが可能です。測定を終えた方は、ご自身の聴力の特性を客観的に把握するためにも、ぜひこのグラフを確認してみることをお勧めします。このデータが、AirPods Proをパーソナライズされた補聴機能として動作させるための基礎情報となります。
ステップ2:外部音取り込みモードへの切り替え
このヒアリングチェックを完了しただけでは、AirPods Proが自動的に補聴器になるわけではありません。次に操作する必要があるのは「ノイズコントロール」の設定です。
設定を「外部音取り込みモード」にすることで、AirPods Proを装着しているにもかかわらず、外部の音がiPhoneを経由してユーザーの耳に届けられるようになります。これが、いわゆる「補聴器モード」と呼ばれる状態です。重要な点として、この機能はiPhoneを携帯していることが前提となります。AirPods Pro自体に内蔵されているマイクで拾った外の音を、iPhone側で処理し、ヒアリングチェックで判明した聞こえの特性に合わせて調整(増幅や補正)した上で、イヤホンを通じてユーザーにフィードバックするという仕組みだからです。つまり、ワイヤレスイヤホンとしての機能に、外の音を調整して聞かせるという機能が“ついでに”付加されているイメージです。
実際に使ってみた感想:違和感と脳のチューニング
Appleのヒアリング補助機能は、自動的にノイズを除去し、特に人間の声などの必要な音をクリアに聞き取れるように調整するという仕様です。しかし、実際に試した初期段階では、残念ながら「期待通り」とまではいきませんでした。
これは、補聴器の世界では一般的に知られている現象で、高価な補聴器(数十万円クラス)を使用する際にも同じことが起こると言われています。今まで聞こえていなかった音が急に増幅されて聞こえるようになることで、脳がその新しい音のバランスにチューニングを合わせるまでに、一定の「学習期間」が必要なのです
私自身も体験しましたが、初期段階で特に強く感じたのは、生活音の違和感です。例えば、戸を閉める「バタン」という音や、食器同士が触れ合った際の「カチッ」という高い音が、まるで雷鳴のように強烈に増幅されて聞こえ、不快感や耳への負担を感じ、正直に言って「堪えがたい」と思いました。この期間を乗り越えて使い続けることで、脳内の「機械学習」が進み、最適バランスに調整されるのでしょうが、今回の検証では評価用のお試し使用に留めたため、初期段階で中断しました。
総評:実用性と今後の可能性
私には過去に、かなりの費用を投じて「本物の補聴器」を購入した経験があります。しかし、その際も同様に、増幅された音への違和感に慣れることができず、結局使用しなくなってしまいました。また、超小型の電池が短期間で消耗し、頻繁に交換する必要があったことも、利用を止めた一因でした。
この経験から考えると、AirPods Proのヒアリング補助機能が引き起こす音の違和感は、本物の補聴器の初期段階における違和感と「似ている」と感じました。逆に言えば、このAirPods Proで「耳を慣らす」トレーニングを積めば、軽度の難聴程度の方であれば、そこそこ実用に耐えるのではないかという可能性も感じました。
このヒアリング補助機能は、本来、イヤホンを装着して音楽などを聴いている時でも、周囲の音を遮断せずに聞きたいという目的のために開発されたものです。したがって、最初から「本格的な補聴器」として使用するのではなく、まずは周囲の音も聞こえる状態で音楽を楽しむための**「外部音取り込み」機能の強化版**として活用し、その使用に慣れてきた段階で、スポット的に補聴器的な利用を試みるというアプローチが、最も無理なく実用的な使い方であると言えるでしょう。手軽なワイヤレスイヤホンが持つ新たな可能性として、今後の進化に期待したいところです。