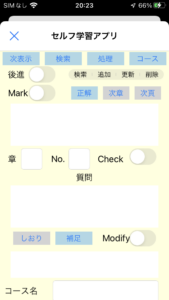歴史の光彩を放つ若き外交官:伊東マンショの生涯

伊東マンショは、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍したキリシタンであり、カトリック教会の司祭です。特に、わずか13歳で天正遣欧少年使節団の主席正使という大役を担い、ローマ教皇に謁見するという日本の歴史上画期的な偉業を成し遂げた人物として知られています。本コラムでは、戦乱の世に生まれ、故郷を追われながらも信仰の道を見出したマンショの生涯をたどります。彼がヨーロッパで果たした外交的役割、帰国後の司祭としての活動、そして近年発見された肖像画が示す、彼の不朽の功績と国際的な足跡について、その光彩に迫ります。
故郷を離れ、運命の出会いへ
伊東マンショ(Mancio、伊東満所、1569年頃 - 1612年)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍したキリシタンであり、カトリック教会の司祭です。洗礼名であるマンショの名で知られ、本名は伊東祐益(すけます)。日向国児湯郡(現在の宮崎県西都市)の都於郡城にて、日向伊東氏の一族として生まれました。しかし、わずか8歳の頃、伊東氏は島津氏の侵攻により敗れ、マンショは家臣に背負われ、親類である大友宗麟を頼って豊後国(大分県)へ退去する波乱の幼少期を過ごします。この豊後で、宣教師ペドロ・ラモンと出会ったことが、10歳のマンショの生涯を決定づける運命的な出来事となりました。彼はキリスト教の教えに触れ、洗礼を受けて司祭を志し、肥前国有馬庄のセミナリヨ(神学校)に入りました。
天正遣欧少年使節の主席正使として
当時、巡察師として日本を訪れていたイエズス会のアレッサンドロ・ヴァリニャーノは、日本の布教事業再建と邦人司祭育成のため、キリシタン大名の名代として使節をローマに派遣することを計画します。セミナリヨで学んでいたマンショを含む4人の優秀な少年たちに白羽の矢が立てられ、マンショは大友宗麟の名代として主席正使という大役を担うことになりました。天正10年(1582年)、マンショ、千々石ミゲル、原マルチノ、中浦ジュリアンの4名は長崎を出航。約8年半にわたる大航海の末、彼らはリスボン、イタリアへと渡り、ローマで教皇グレゴリウス13世、そしてシクストゥス5世と謁見するという、日本の歴史上画期的な偉業を成し遂げました。この旅の途上、トスカーナ大公妃ビアンカとの舞踏会でのエピソードに見られるように、マンショは礼儀正しく、立派に使節としての責務を果たし、西洋で初めて日本を紹介し、「日本」の存在を世界に強く印象付けました。また、帰国時には活版印刷機や西洋音楽などの文化を日本に伝え、文明交流の先駆者となりました。
司祭としての生涯と最期の地
天正18年(1590年)に帰国したマンショらは、翌年、聚楽第で関白・豊臣秀吉と謁見します。秀吉は彼らを厚遇し、マンショに特に強く仕官を勧めましたが、彼は司祭になる決意を貫き、これを辞退しました。その後、司祭になるための勉学を続け、文禄2年(1593年)にイエズス会に入会。慶長6年(1601年)からはマカオのコレジオで神学の高等課程を学び、慶長13年(1608年)に原マルティノ、中浦ジュリアンと共に司祭に叙階されました。司祭となったマンショは、豊前小倉を中心に布教活動を行いましたが、慶長16年(1611年)に領主・細川忠興によって追放され、中津、さらに長崎へと移り住みます。長崎のコレジオで教えながら、慶長17年10月21日(1612年11月13日)に病のため、43歳の短い生涯を閉じました。
現代に蘇る若き日の肖像
伊東マンショの歴史的意義は、近年再評価が進んでいます。2014年には、イタリア北部で、ルネサンス期の画家ドメニコ・ティントレットによるものと推測されるマンショの肖像画が発見されました。この肖像画は、天正遣欧少年使節がヴェネツィアを訪問した際に描かれたと考えられており、彼の若き日の姿を今に伝える貴重な資料です。絵の裏側には、「ドン・マンショは日向国王の孫/甥で、豊後国王フランチェスコより教皇陛下への大使、1585年」という説明が書き込まれており、彼が担った外交的役割の重要性を示しています。この肖像画は、「未知への挑戦と異文化との出会い」というテーマを象徴する作品として、2025年開催の大阪万博イタリア館でも展示されるなど、大きな注目を集めました。激動の戦国時代において、清らかな信念に生きた司祭、伊東マンショ。彼は、西洋へ渡った最初の日本人外交官の一人として、また、日本とヨーロッパの文化交流の先駆者として、現代においても私たちに国際的な視野と揺るぎない志の重要性を伝え続けています。