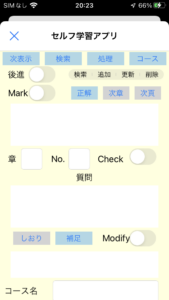【ハロウィーンってなに?】「E.T.」から始まった探求!仮装とお菓子の裏にある2000年の歴史

ハロウィーンといえば、皆さんは何を思い浮かべますか?
私が子どもの頃、このイベントを強く意識したきっかけは、スティーブン・スピルバーグ監督の映画「E.T.」でした。作中、主人公の男の子がE.T.の存在を隠すため、お化けの仮装をさせて自転車のカゴに入れ外出。そして、E.T.の超能力で自転車ごと満月の夜空を飛ぶ、あの幻想的なシーンは今も忘れられません。
「アメリカにはこんな風習があるんだ、面白いな」と感じたのが始まりです。それが近年、日本では爆発的に広がり、電車に乗るとゾンビやアニメキャラの仮装をした人々を見るのが日常になりました。こうしてハロウィーンが恒例行事となった今だからこそ、「そもそもハロウィーンって何だろう?」と、その起源を深く調べてみることにしました。
ハロウィーンの起源は「お盆」と「大晦日」が一緒になった古代の祭り
現在、毎年10月31日に行われるハロウィーンですが、そのルーツは、約2000年前の古代ケルト人の祭り「サウィン祭(Samhain)」に遡ります。
古代ケルトの暦では、10月31日はちょうど一年の終わり、大晦日にあたります。彼らはこの夜、夏の終わりと冬の始まりを祝い、同時に「死後の世界と現世を隔てる扉が開き、先祖の霊が家族に会いに戻ってくる」と信じていました。この点は、まさに日本のお盆と似ています。
しかし、問題は、ご先祖様だけでなく、悪霊や魔物までが一緒に現世にやってきて、作物に悪さをしたり、人間に災いをもたらしたりすると恐れられていたことです。
その後、ケルト文化圏にキリスト教が広がる中で、この風習はキリスト教の「諸聖人の日(All Hallows' Day)」と融合します。
- 諸聖人の日(All Hallows' Day):11月1日。すべての聖人(Hallow)を記念する大切な祝日。
- ハロウィン(Halloween):諸聖人の日の前夜(All Hallows' Eve)が短縮された言葉で、10月31日を指します。
つまり、ハロウィーンは、古代の収穫祭と死者の祭り、そしてキリスト教の祝日が結びついて生まれたイベントなのです。
仮装の本当の意味は「悪霊から身を守る知恵」
現代のハロウィーンの最大の特徴である「仮装」は、単なるコスプレ大会ではありません。その習慣は、悪霊や魔物から自分の身を守るための、切実な知恵から生まれました。
- 悪霊の仲間になりすます: 人々は、現世に現れた悪霊と同じような恐ろしい格好に仮装することで、「私たちは人間ではない、悪霊の仲間だ」と思わせ、悪さのターゲットから逃れようとしました。
- 悪霊を追い払う: または、逆に恐ろしい怪物に扮して、本物の悪霊を怖がらせて追い払うという意味合いもあったとされています。
現代では、この宗教的・魔除け的な意味合いは薄れ、魔女やゾンビだけでなく、好きなキャラクターに扮して楽しむ、娯楽性の高いイベントへと変化していきました。
「トリック・オア・トリート」は施しを求める古代の風習
子どもたちが楽しみにしている「Trick or Treat!」(お菓子をくれないといたずらするぞ!)という遊びにも古い起源があります。
これは、中世のヨーロッパで行われていた、貧しい人々や子どもが家々を回って食べ物や施しをもらう風習が元になっています。
- ソウルケーキの風習: 死者の魂のために祈る人々が、家々を回ってソウルケーキというお菓子をもらう慣習がありました。
- 「ガイジング」: スコットランドなどでは、仮装した人々が芸を披露して食べ物をもらう風習(Guising)がありました。
これらの風習が北米に渡った後、「お菓子(treat)をくれなければ、いたずら(trick)をする」という現代の合言葉へと進化しました。元をたどれば、死者を慰め、貧しい人に施しを与える、相互扶助の精神から生まれたものなのです。
これも日本で馴染みのある風習です。私の故郷では正月に獅子舞が各家を周り獅子に頭を噛んでもらうとその年は幸せになるということで、獅子舞がくるともてなしてご祝儀を出したりしていました。これは貧しい人が正月を無事すごせるように獅子舞をやってくれた代わりにお金とか食べ物を施すというものだったらしく、こういった面でも、ハロウィーンの習慣は日本に馴染むのかもしれませんね。
まとめ:ハロウィーンを「日本のお盆」感覚で楽しもう
こうして起源を調べてみると、ハロウィーンの核には、日本人が大切にする「お盆」とよく似た、ご先祖様を敬い、災いから身を守りたいという感覚があることが分かりました。
近年、日本でのハロウィーンは、その歴史的背景よりも「自由な仮装を楽しむお祭り」として広まりました。しかし、本来の「悪霊を遠ざけ、ご先祖様の霊を敬う」という趣旨を踏まえれば、無軌道な騒ぎではなく、もう少し厳かで平和な、成熟したイベントとして楽しむことができるはずです。
今年は、仮装の楽しさに加え、その裏にある2000年の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。