シニアしごとEXPO2025参加レポート:65歳からの「働く」を考える
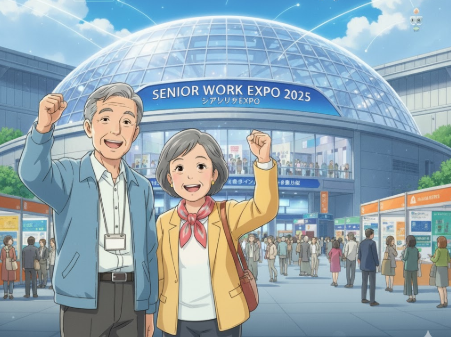
令和の定年後:誰にでも訪れる「働く」の転換期
先日、東京都が主催する「シニアしごとEXPO2025」に参加してきました。ここで言う「シニア」とは、主に50代以降の方々を指しています。このイベントは、再就職を支援するための活動、いわゆるハローワークが主催する大規模なイベントの一つです。
「職安」と聞くと、ついネガティブなイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、退職した人が誰でも利用する場所であり、その目的は大きく二つあります。一つは、文字通り仕事を探すため。もう一つは、求職者給付金を取得するためです。この給付金は、離職の翌日から最長1年間、求職活動中の生活を支える大切なものです。
今回、私がこのEXPOに参加した最大の関心事は、65歳以上の求職者が本当に仕事を見つけられるのか、という点でした。2025年から企業は、従業員が希望すれば65歳まで雇用を延長することが義務化されました。これによって、事実上の定年退職は65歳というのが、もはや令和の常識となっているからです。超高齢化社会の日本において、65歳以降も「働く」という選択肢は、現実的かつ重要なテーマとなっています。
講演レポート:自分らしさを再発見し、健康寿命を延ばす
会場では、シニアの就業に関する示唆に富む講演やトークショーが開催されていました。
超高齢化社会 健やかに自分らしく働くヒント
最初に拝聴したのは、株式会社セカンドエール代表取締役の髙橋伸典氏による講演「超高齢化社会 健やかに自分らしく働くヒント」です。髙橋氏は、長年一つの職業に就いてきた人には、自分自身では気づきにくい「強み」が必ずあると強調されました。その強みを徹底的に「棚卸し」し、セカンドキャリアに活かすことの重要性を説かれました。
しかし、自分自身の強みを客観視するのは非常に難しいものです。まさにこういう時にこそ、ハローワークの相談窓口などにいるキャリアコンサルタントの方々の専門的なサポートが必要になるのだろうと感じました。
また、興味深かったのは「働く」という行為が、結果的に健康増進に繋がるというお話でした。仕事を通じた適度な運動、知的な刺激(脳トレ)、そして社会とのつながり(孤独感の解消)が、健康寿命を延ばす上で極めて効果的であるという視点は、働くことの新たな意義を教えてくれました。(以下のリンクにはアフィリエイトリンクが含まれます)
榊󠄀原 郁恵さんトークショー:「わたしらしく、もっと輝く。」
続いて、タレントの榊󠄀原郁恵さんが登場されたトークショー「第二の人生も、わたしらしく、もっと輝く。」を聞きました。かつての「郁恵ちゃん」のイメージそのままに元気な榊󠄀原さんも、実は今年で66歳。シニア世代の代表として呼ばれたわけです。
芸能界は定年がないため、現在も「ファーストキャリア」のまま頑張っているという彼女は、「セカンドキャリアへの切り替え」という感覚は自分にはない、と率直に語られました。しかし、そんな彼女が最大の武器とするのは、「いかに元気でいるか」ということ。運動や食事など、日々の健康管理を意識していると明かされました。また、芸能界の先輩方が現役で活躍し続ける姿を見て、「自分もまだまだ頑張れるし、頑張らなければ」という意欲を語る姿は、多くのシニアに勇気を与えたことでしょう。
シニア就業の未来とAI:避けられないITリテラシーの波
最後の講演は、シニア専門の転職紹介エージェントサイトを運営する、株式会社シニアジョブの中島康恵氏によるものでした。この「シニア専門」という点が大変興味深く、後ほど登録してみようと思っています。
サブタイトルにもあった「AI」についての話は、特に示唆に富んでいました。中島氏が強く訴えられたのは、「AIをうまく使いこなす能力は、シニアにも不可欠」という点です。
その具体的な理由として、まず挙げられたのが「書類選考の突破率の向上」です。中島氏は、シニア世代の応募者の中には、履歴書や職務経歴書の書き方で書類審査に落ちてしまうケースが非常に多いと感じているそうです。ここでAIに相談しながら書類を作成することで、就職率を上げられると指摘されました。さらに、AIに面接官の役をさせて面接の練習をしたり、実際に就職した後もITツールを使って業務を行うケースが増えているため、ITリテラシーはもはやシニアにも求められるスキルだとのことでした。これからのシニア就業においては、経験だけでなく、新しい技術への適応力が重要な鍵となりそうです。
EXPOを終えて:令和を生きるシニアの覚悟
今回のEXPOに参加して、定年退職後に仕事を続けている人が全体の50%以上(若い年代では75%近く)いるという事実を知り、定年退職して悠々自適の余生を送る、というイメージは、令和の現代においては「夢のまた夢」だと痛感しました。
しかし、これはネガティブな話ばかりではありません。余生を楽しむ=暇を持て余す、ということにもなりかねません。結局、何らかの形で社会との繋がりを維持した方が、精神的にも満たされ、幸せに生きられるのではないでしょうか。それは、まさに「働き、社会に貢献する」というやり方に行き着くのだと思います。
今回のEXPOは、自分自身の今後の働き方について深く考え、AIなどの新しい知識も身につけて今後に備えようと、心を新たにする貴重な機会となりました。



